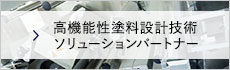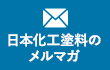高機能性塗料コラム
第2回、なんでくっつかないの?
投稿日:2018/3/19

こんにちは。「こんな塗料できないの?」に私たちが答えます。
高機能性塗料設計技術ソリューションパートナーの遠竹(とおたけ)です。
私からは今回、次回の2回にわけて「離型コーティング剤」について紹介いたします。
早速ですが、みなさんは「離型」というと何を想像されるでしょうか?
身近なもので言えば、宅急便等の伝票を貼る際に剥がす離型紙、
シールの台紙や料理をする際に食材がフライパンにくっつかない「テフロン加工」等が浮かぶと思います。
離型紙に使用されるのは「シリコーン樹脂」
テフロン加工に使用されるのは「フッ素樹脂」
どちらも「離型」という概念では同じです。
ではなぜ、両者とも粘着剤や食材がつかないのでしょうか?
モノとモノがくっついたり剥がれたりするときは、そのモノの界面で化学的な相互作用が働きます。
その相互作用を左右するのが、界面の「極性」になります。極性は表面の極性基の量に左右されます。
化学的相互作用が高い、すなわち極性が高い場合、モノの界面には極性基(親水基)が多く存在し、
モノをくっつけようと働き、下図左のように液体はぬれやすくなります。
逆にモノの極性が低い場合、界面にはくっつけようとする働きをする極性基が少なく、
非極性基(疎水基)が多く存在するため、下図右のように液体はぬれにくくなり、
モノは剥がれやすくなります。
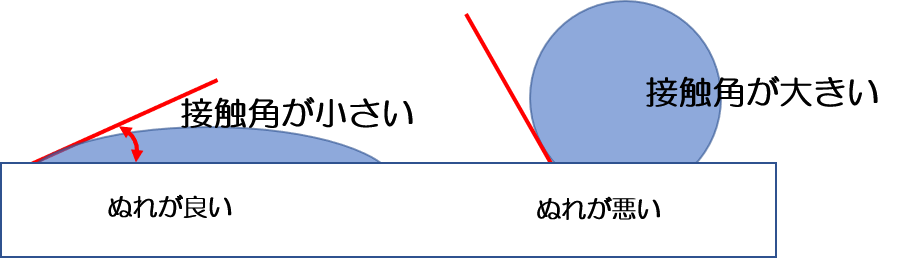
したがって離型という、より剥がしやすくする技術には、
モノの表面を低極性にするということが大事になります。
フライパンの表面には、フッ素樹脂で施したテフロン加工という技術が用いられますし、
シール等の離型紙には、シリコーンという骨格をもったコーティング剤が塗られています。
この共通点は、いずれも「極性」が低いということです。
○テフロンの構造
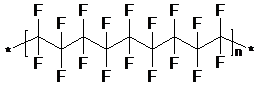
○シリコーンの構造
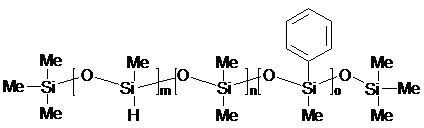
それでは次回、各種離型コーティング剤の特徴について紹介させていただきます。